1,000円越えも当たり前。文庫本が高く分厚くなった合理的な理由
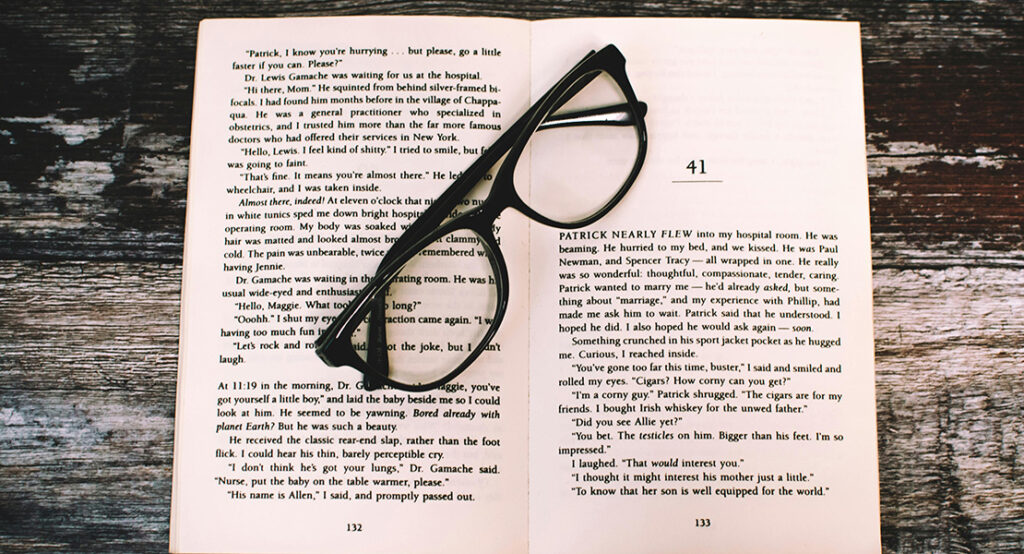
最近、「構造と力」、「アルジャーノンに花束を」、「百年の孤独」など、歴史的な名著とされる本が続々と文庫化されています。近年の大ヒット作である、ユヴァル・ノア・ハラリの「サピエンス全史」も、SF小説「三体」も文庫化。判型も小さく値段も手頃なので、Kindleを持っていない「本は紙派」のわたしにとってはありがたい傾向なのですが、一方で、文庫本がどれも高額になっていることには驚きを隠せません。
そもそも文庫に限らず、紙の本はどんどん高くなっています。しかし、文庫本といえば数百円で買えるものだと思っていたところが、1,000円札を持っていっても足りないぐらいなのですから、ちょっと踏み止まって考えたくもなります。
昔は文庫本が安くて、新書本はそれより少し高かったような印象があったのですが、今は文庫本の方が高い気がします。もちろん、新書も高くなっているのですが、文庫が追い越してきているのです。
それは、文庫が新書に比べて分厚くなってきているからではないでしょうか。元々新書は手軽に読めるボリュームという点も特徴であったのですが、文庫は小さい割にどこまでも濃密にできるような柔軟性があり、「擬音語・擬態語辞典」のように、文庫版の辞典があるぐらいなのです。
塩野七生著「ローマ人の物語」は、ハードカバーの書籍として出版された後、2002年に文庫版が刊行されました。その1巻の前書きには、文庫本の発祥についてこう書かれています。
「こうして、西暦一五〇〇一年刊行のヴェルギリウス作の『アエネイアス』を一番手にして、プラトン、アリストテレス、キケロ、カエサルと、アルドゥス社(アルドのラテン読み)出版の文庫がつづきます。製本の際の折り方から「オッターヴォ」(八つ折)と呼ばれた小型本でしたが、厚さのほうも、当時の男たちの一般的な服装であったシャツとその上に着ける胴着の間にはさめる程度。なにしろ、「ポータブル」(イタリア語ならばポルタービレ)でなければならなかったのですから。そして、アルドが出版したいと思った書物の作者はほとんどが長編作家であったので、アルド考案の「文庫」は分冊が普通になりました。」
ここから推測するのですが、おそらく文庫本が分厚く、高価になっているのは、そもそも紙の本が売れなくなっていく傾向の中で、上下巻や複数巻に分冊すると、結果的に数冊買う必要があり、より高くついてしまう、そしてより一層売れなくなってしまうので、一冊にまとめられるなら、高くてもいいからなるべく一冊にしてしまおう、という流れなのではないでしょうか。「ローマ人の物語」はハードカバーの単行本で全15巻ですが、文庫版は全43巻。約3倍の数になっているのは、作者のこだわりで、「シャツとその上に着ける胴着の間にはさめる程度」であるべきとのこだわりがあったからです。実際にわたしも通勤時に読んでいますが、カバンから水筒を出したいときなどにお尻のポケットにスッと差し込めるのは、とても便利です(しかも軽いので荷物にならない!)。どうせ一冊が400ページも500ページもあったところで通勤時間中に読めるのはせいぜい数十ページなので、機能的には分冊して薄くしてくれた方が便利に違いないのですが、今の時代は経済合理性がそれを許してくれないようで、「三体」も「サピエンス全史」も、単行本が上下巻なら、文庫版も上下巻でした。
ちなみに「ローマ人の物語」文庫版第1巻の初版本が手元にあるのですが、約200ページのこの本、表4を見ると「定価:本体400円(税別)」と書かれています。2002年当時の消費税は5%でしたから、420円で買えたということですね。
では現在も発行され続けているこの本、今いくらでしょうか?
正解は、2024年7月現在で、「605円(税込)」。
薄くて安い文庫本、という、読者が本当に欲しいものは、今やもう手に入らない時代となってしまったようです。




